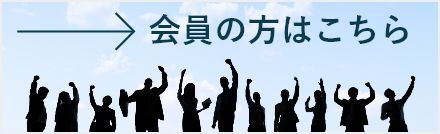1920年(大正9年)10月6日 法曹同志会設立
大正デモクラシーの中、新しい時代思潮が東京弁護士会の少壮会員らをして結成されたのが、法曹同志会です。創立総会は築地「精養軒」で開催されました。創立総会で採択された綱領の中には、若い会員に優先権を与えるような条項ないし文言があったとのことです。
1948年(昭和23年) 法曹親和会結成
法曹大同会、二一会、東京法曹会、法曹同志会の四会派が結束し、法曹親和会を結成しました。その後、約20年間、法曹同志会は法曹親和会にて活動。
1967年(昭和42年) 法曹親和会を脱退(幹事長 本林譲)
法曹親和会を脱退後、法曹同志会内に機構改革委員会を設置し、機構改革をスタートしました。会則を改正し、幹事会(執行部)のほかに評議員、弁護士会会務、法令実務研究、総務の三常置委員会を設ける等機構を一新しました。なお、この当時の会員数は200余名、年間予算約150万円でした。
その後、約16年、法曹同志会は小会派として活動しました。
1983年(昭和58年) 法友会への加盟を決議(幹事長 本林徹)
法友会への加盟に先立ち、瀧澤國雄や岡村了一らが主導する「わが会の路線問題を考える」会が数年にわたって開催され、議論の結果、意見収束をし、上記決断の運びとなりました。 当時の会員数は240余名、年間予算約1200万円でした。
<法友会加盟に際しての宣言文>
法曹同志会はここに法友会に加盟する。
ー中略ー
しかるに、近年深く時流の赴くところを察するに、わが国現時の諸状況の中で、弁護士の職務に寄せられる世の期待と信頼は日を逐うて愈々盛んなものがある。
かかる動向裡にわが会は、貴重な独歩16年余の間に蓄積し得たものを、より大きくより理想的な同志的結合の中において活用することが、この際自己の使命に最も忠実なる所以であるとの大勢の見解に基づき、すなわちこれを全会の討議に付した結果、創立64年の伝統・会風に照らして、今後相結んで久しい調和を保つべき母体として法友会加盟の道を選択するに至った次第である。
わが会の右決意に対して、法友会が夙に示されてきた絶大な厚意を多謝し、同会加盟の暁において、われらはこれに応えて十分な信義・友愛・貢献の実を示さんことを念願する。 わが会はここに新しき同志と手を携え、弁護士会の公正明朗な運営に力を尽くし、もって弁護士の権威を高揚し、すすんで日本国憲法の基盤に立つ理想の実現に寄与せんとするものである。右宣言する。